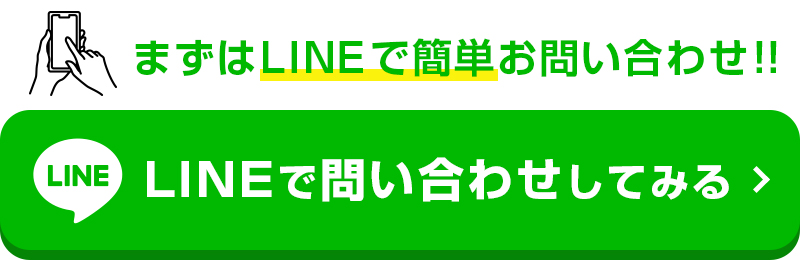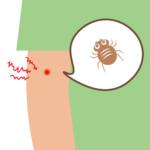下痢が止まらない!?黒い!?原因や症状が出た時の対処法
投稿日: 2021年05月15日 | 更新日: 2024年03月08日
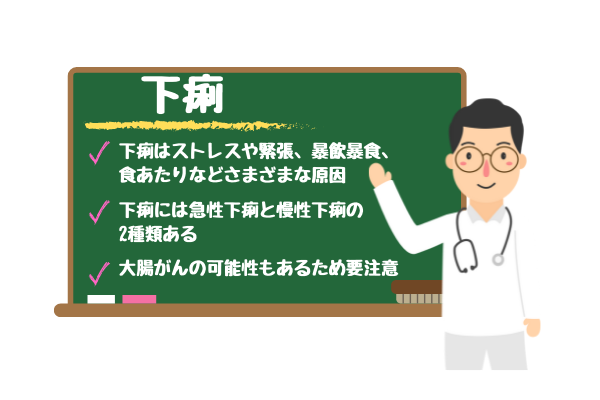
便は健康のバロメーターです。体調が崩れ、お腹の調子が悪くなると、下痢を起こしやすくなります。
下痢をすると、からだに力が入らず頭もぼんやりしますし、トイレの不安で外出がままならない….なんてことも。
このようなつらい状態からは、少しでも早く解放されたいですよね。
そのままにしておくと怖い病気など重症化する可能性もあります。
今回は、そんな辛い下痢の原因や正しい対処法について紹介します。
解熱剤のことなら家来るドクターに相談△
目次
下痢症状の原因の正体について

一口に下痢といっても軽いものから重いものまであり、黒いものが出てくる時など症状はたくさんあります。
休日診療・夜間診療に行くべきか、あくる日の朝まで様子をみていいものか、迷われることも多いですよね。
まず、下痢症状がいつから発生しているかで急性下痢と慢性下痢に分かれます。
概ね4週間が急性と慢性を分けるひとつの目安となります。
急性下痢の場合はほとんどウイルス性腸炎で、自然軽快することがほとんどです。
- 急性下痢・・・2週間落ち着く下痢。ほとんどがウイルス性。
- 慢性下痢・・・4週間以上続く下痢
急性下痢の原因
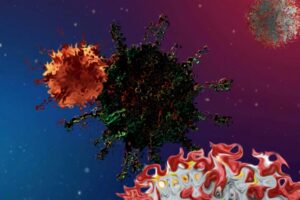
急性下痢の多くは感染性胃腸炎であり、大半がウイルスによるものと言われています。
感染性胃腸炎は、大きく分けてウイルス性胃腸炎と細菌性胃腸炎があります。
ウイルス性胃腸炎
ウイルス性腸炎は嘔吐下痢症などとも言われております。
よく知られているウイルスにはロタウイルス、 アデノウイルス、 アストロウイル ス、 ノロウイルス、 サッポロウイルスなどがあります。
どちらかというと冬場に多い感染症です。
ウイルスに対して抗菌薬は効果がありませんので、対症療法として鎮痛剤、制吐剤や整腸剤を使用することになります。
細菌性胃腸炎
一方、 細菌性腸炎は食中毒などといわれ、夏場に多い感染症です。
カンピロバクター(加熱不十分な鶏肉、牛レバーなど)、サルモネラ(牛肉、鶏肉、卵、魚など)や腸管毒素原性大腸菌が最もポピュラーです。
意外かもしれませんが、細菌性の場合でもほとんどは抗菌薬を使用しません。
抗菌薬を使用しなくても改善する場合がほとんどだからです。
さらに、高齢者や免疫力が弱っている方に抗菌薬を使用すると菌抗体現象(大腸の常在菌が抗菌薬により死滅し、通常繁殖しない病原体が増殖すること)が起こり、クロストリジウム・ディフィシル腸炎という特殊な腸炎が起こることもあるので、抗菌薬は安易に使うべきではありません。
ただしカンピロバクターの場合など腹痛や血便など症状が重くなるケースには抗菌薬を使うこともあります。
これは病院で便の細菌検査をすることで判別できます。
解熱剤のことなら家来るドクターに相談△
慢性下痢の原因

慢性下痢で最も多いのが過敏性腸症候群です。
主にストレスにより大腸の過剰な蠕動(ぜんどう)が引き起こされる
ことが原因であり、ストレスの軽減や生活習慣の改善が必要です。
|
「過去3か月、1か月につき3日以上にわたって腹痛や腹部不快感がある」 「排便により症状が改善する」 「排便頻度や便の形状が変化する」 |
といった症状に当てはまる方は過敏性腸症候群である可能性が高いです。
他に遺伝的な疾患と考えられている潰瘍性大腸炎やクローン病があります。
血便や体重減少を伴う慢性下痢で、血縁者にも同様の疾患を患っている方がいる場合はその可能性があります。
専門的な診察や治療が必要ですので、必ず病院を受診してください。
他に稀なケースとしては慢性膵炎による脂肪消化不全による下痢、胃薬が体に合わず起こる下痢もあります。
また、便秘に対して下剤を使用している方の場合、下剤の種類が体に合わない・服用量が多いことが原因で逆に下痢になってしまっていることもあります。
いずれのケースにしても、まずはバイタルサインの測定と医師による診察で重篤度を判断することが最も重要です。
判断に困った場合はお気軽に家来るドクターに御相談ください。症状に応じて連携医療機関の医師が診察に伺います。
下痢のタイプ分類
外因性下痢と内因性下痢、急性下痢と慢性下痢消化管での水分出納バランスからみると、下痢は以下の4つに大別できます。
腸からの水分吸収が妨げられる「浸透圧性下痢」
食べた物の浸透圧(水分を引き付ける力)が高いと、腸で水分がきちんと吸収されないまま排便されるため、下痢になります。
牛乳を飲むとおなかを壊す乳糖不耐症の下痢も、これに当てはまります。
糖分の消化吸収が 良くないときや、人工甘味料を摂り過ぎたときなどに起こります。
腸からの水分分泌量が増える「分泌性下痢」
腸は水分を吸収するだけでなく、腸液などの水分の分泌もしています。
その分泌量が多いと当然、 便の中の水分が多くなり下痢になります。
このようなことが起きる原因としては、腸に入った細菌 による毒素やホルモンの影響など、いろいろあります。
腸の通過時間が短くなる「ぜん動運動性下痢」
腸は、食べた物を口側から肛門側に移動させるために、ぜん動運動を繰り返しています。
ぜん動運動下痢の 「浸透圧性下痢」と 「分泌性下痢 腸液」が活発すぎると、食べた物が短時間で腸を通過してしまい、水分の吸収が不十分になって下痢になります。
過敏性腸症候群や甲状腺の病気(バセドウ病)などが該当します。
炎症により滲出液が増える「滲出性下痢」
腸に炎症があると、そこから血液成分や細胞内の液体などが滲み出て、便の水分量を増やします。
また、腸からの水分吸収が低下することも関係してきます。
クローン病や潰瘍性大腸炎などが該当します。
|
これとは別に、原因がからだの外から入ってきた物にあるのか(外因性)、それとも、からだの中で起きたことなのか(内因性)、という分け方もできます。
例えば、暴飲暴食による下痢や食中毒による下痢は「外因性の下痢」ですし、過敏性腸症候群などは「内因性の下痢」です。
また、急に始まって短期間で治まる「急性の下痢」と、 長く続く「慢性の下痢」という分け方もあります。
一般に、急性の下痢は外因性、慢性の下痢は内因性です。
解熱剤のことなら家来るドクターに相談△
下痢の原因チェックリスト
下痢になったら、まずはその原因を確かめましょう。
原因により対処法は異なるため2、3日前から症状が起こる前後の思いあたる原因を探りましょう。
以下のチェックリストをご活用ください。
| 食あたり |
| □ 賞味期限切れ食品を食べた |
| □ 調理して時間の経った料理を食べた |
| □ 生もの・半生食(刺身、生カキ、生野菜、牛肉、鶏肉、卵など)を食べた |
| □ お弁当やサンドイッチを食べた |
|
□ 旅行先の水道水、硬度の高い飲料水などいつもと違う飲み水を飲んだ |
| □ 旅行先で氷の入った飲み物を飲んだ |
| □ 水分を摂りすぎた |
|
□ ビール・お酒を飲みすぎた |
|
水あたり |
| □ 脂肪分・糖分の多い食べ物(揚げ物、焼肉、牛乳、ケーキ、リンゴジュースなど)を食べすぎた |
| □ 刺激の強い食べ物・飲み物(コーヒー、炭酸飲料など)を食べた |
| □ 香辛料の多い料理を食べた |
| □ 普段食べたことのない食べ物・飲み物を摂取した |
| ストレス |
| □ 精神的なストレス(学校・会社に行く前、試験・受験・会議・面接などの大切なイベント前など)を抱えている |
| □ 身体の冷やす(冷房のかけすぎ、気温の変化)ことがあった |
| その他 |
| □ 薬(抗生物質など)の服用 |
| □ 牛乳や乳製品の摂取 |
| □ 風邪(おなかの風邪) |
| □ 過敏性腸症候群(IBS) |
| □ 腸自体の炎症や腫瘍(クローン病、潰瘍性大腸炎等)などの器質的な疾患 |
| 該当なし |
| どれにも該当しない場合や原因がわからない場合は、 症状をチェック |
下痢の症状別の対処法
下痢の症状別に対処法をご紹介いたします。
下痢症状|微熱や高熱寒気がある場合

急性腸炎で微熱を伴うことは多いですが、特に高熱が出た場合はノロウイルスによる腸炎が考えられます。
冬期に多いとされていますが、年間通じて報告されています。
牡蠣などの二枚貝のほか、サラダやサンドイッチのような非加熱食品、またノロウイルスに感染している人の便や吐物にも含まれており、二次感染を起こしやすいのも特徴です。
ノロウイルスは迅速キットを使って便を検査することで診断が可能です。
ただし保険適応が3歳未満もしくは65歳以上に限られており、その他の年齢の方が受ける場合は自費となります。
(悪性疾患の診断を受けている方、臓器移植後の方、その他免疫不全状態と診断されている方はその限りではありません。)
なお、ノロウイルスには特効薬といえるものはありませんので、解熱剤や制吐剤、整腸剤の内服による対症療法がメインとなります。
家来るドクターでは連携医療機関の医師の判断のもと往診して、その場で処方が可能です。
下痢症状|3日以上続いて止まらない場合
ウイルス性腸炎でも細菌性腸炎でも、多くの場合は数日で自然に軽快します。
その間は解熱剤や制吐剤、整腸剤の内服による対症療法を行います。
ただし下痢があまりにもひどい場合、乳幼児やもともと衰弱している高齢者は脱水症、電解質異常(体内の塩分やミネラルバランスの喪失)が起きることがあります。
その場合は、電解質や糖分を含んだ点滴をしてもらうのが望ましいです。
なお下痢がひどいからと言って、止痢剤(下痢を止める薬)を積極的に使用することはありません。
下痢は細菌やウイルスを体外に排出しようとする、人間の体がもつ正常な防疫反応のひとつです。
無理に下痢を止めると病原体が体から排出されず、治るのが遅くなることがあります。
整腸剤で腸内の環境を整えつつ、失った水分や電解質を経口摂取や点滴で補うことが重要です。
下痢が黒い場合の解説と対処法
下痢の便が黒い場合は消化管出血の可能性あります。
血液に含まれるヘモグロビンという成分が胃酸などの消化液に混ざり酸化されることで黒くなることが原因です。
出血部位を特定するためには病院へ行って胃カメラ、大腸カメラを受ける必要があります。
便が黒い場合、第一に疑うのは上部消化管(食道や胃、十二指腸)からの出血ですが、慢性的な大腸からの出血で黒っぽくなることもあります。
潰瘍性大腸炎やクローン病のほか、大腸癌により便に血液が付着したり柔らかく細い便しか出ないようになることがあります。
診断のため可及的速やかに内視鏡検査を受ける必要があります。
家来るドクターでは休日・夜間でも緊急で内視鏡検査を受けた方がいいのか、止血剤等の内服で翌日まで待てるものか、医師の診察により判断します。
お気軽にご相談ください。
解熱剤のことなら家来るドクターに相談△
黒い下痢症状|嘔吐もある場合
黒い下痢だけではなく嘔吐も伴う場合、食事も水分も摂取できず、薬を内服しても吐いてしまう状態は危険です。
脱水症状を起こしてしまうことがあります。
特に自分で症状を言えない乳幼児や高齢者の脱水症状は判断が難しいです。
乳幼児の場合は、
|
「明らかにぐったりしている」 「泣いても涙が出ていない」 「おしっこが出ていない」 「水分も飲めない、飲んでも吐く」 「大泉門(頭の頂部にある頭蓋骨の隙間)が凹んでいる」 |
といったものが脱水症の特徴的な所見になります。
このようなとき、ミルクや水分をがんばって飲ませてしまいがちですが、胃腸炎で消化管の機能が低下しているときは一気に飲ませても吐いてしまうことが多いです。
そのため少量・頻回の摂取が有効です。
少しずつ水分(可能であれば経口補水液やスポーツドリンク等)を摂取し、制吐剤や整腸剤を内服して安静にしていただくのが第一です。
それでも改善しない場合は病院で点滴をしてもらうのが望ましいでしょう。
下痢の症状…もしかしてガン?

大腸がんになると、下痢だけでなく便秘、血便や腹痛、便が細くなるなどの自覚症状が現れることもあります。
ただ、これらは大腸がんが進行してからの症状なので、早期発見がカギとなります。
そのためには、定期的な健康診断を受けることが何よりも重要です。
CT検査が可能な家来るドクター連携クリニックはこちら▼
下痢が黒い!?症状が出た時の対処法|まとめ
このように一言で下痢と言っても診療は多岐にわたります。
多くの場合は対症療法と水分の補給で様子をみていただいて大丈夫です。
しかし稀に重篤化することもありますのでご心配の方はお気軽に家来るドクターへご相談ください。
関連記事:男女別に知ってほしい貧血の原因と予防に効く食べ物!
家来るドクターでの治療

家来るドクターでは症状に応じて連携医療機関の医師が診察に伺い、必要に応じてその場で整腸剤や制吐剤、解熱鎮痛剤も処方することが出来ます。
また点滴が必要と判断した場合は病院への紹介も含め、臨機応変に対応いたします。紹介状の発行も可能です。
夜間、休日でお困りの場合はご遠慮無くお気軽に家来るドクターにご相談ください。
解熱剤のことなら家来るドクターに相談△
役立つ医療の最新情報発信しております。
フォローよろしくお願いいたします!
【監修医師】

西春内科在宅クリニック 消化器内科 近藤
こちらの記事もオススメ
〇関連記事:大人の胃腸炎の症状を改善する方法|嘔吐や下痢の原因
〇関連記事:吐き気がみられる腹痛で病院を受診する目安は?考えられる原因や対処方法